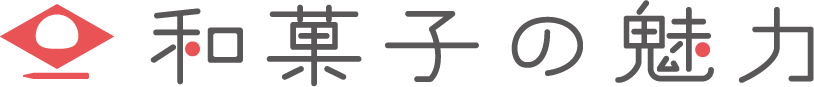由来・歴史
うぐいす餅の歴史は、安土桃山時代の大和国(奈良)で開幕しました。
豊臣秀吉の弟・秀長の家来で菓子職人の菊屋治兵衛が、秀吉をもてなす茶会で自作の餅菓子を献上したところ、秀吉が気に入り「うぐいす餅」と銘じたことに由来しています。
その後、うぐいす餅の名前は、治兵衛が郡山城(現大和郡山市)の大門を出て1軒目の場所に開店したことにちなんで、「御城之口餅」(おしろのくちもち)称されるようになりました。
現在は、うぐいす餅、鶯餅、御城之口餅と呼び名が混在していますが、御城之口餅はうぐいす餅の通称として使用されています。
一方、草創期のうぐいす餅は、現在主流の青きな粉ではなく、黄大豆による普通のきな粉をまぶしていました。そのため、色合いも現在のウグイス色(黄緑)ではなく、”黄色いきな粉色“だったと考えられています。
しかし、うぐいす餅は時とともに変化していき、あざやかな黄緑、すなわちウグイス色に近づいていきました。
特に青きな粉を用いるようになってから、うぐいす餅=黄緑の印象が決定的となり、形状も含めたうぐいす餅のビジュアル全体の標準が固く定まりました。
そして、うぐいす餅自体も奈良から各地へ広がっていき、全国区の餅菓子となったのです。
カラーは現在も黄緑が主流ですが、本家菊屋など普通のきな粉をまぶしている老舗店舗では、うぐいす餅の原風景をしのぶことができます。
特徴
うぐいす餅は、求肥にあんこを包んでうぐいすの形に造形し、うぐいす粉(青きな粉)まぶして食べる和菓子です。
日本三鳴鳥の一つ「うぐいす」をモチーフとしており、文字通りうぐいすを模したデザインをはじめ、若葉色やモスグリーンなどあざやかなウグイス色も美しく季節感たっぷりで、桜餅と並んで春の餅菓子として親しまれています。
味わいは上品にして美味。餅菓子共通のモチモチ食感やあんこの旨味は言うまでもなく、うぐいす粉(青きな粉)による独特の甘み、歯ざわり、程よい香ばしさが求肥のあんこ餅にフィットして絶品です。
うぐいす餅の材料と作り方は、求肥にこしあんを包んでうぐいす粉をまぶすのがスタンダードですが、生地に白玉粉、あんこにつぶあん、仕上げの粉には普通のきな粉や抹茶入りきな粉を使用する場合もあります。
うぐいす餅は地域によって特徴が異なりますが、象徴的な魅力は「うぐいす粉=青きな粉」が担っています。
うぐいす粉は、青大豆を炒ってひいて粉末にした風味のよいきな粉です。青大豆は一般的なきな粉の素材である黄大豆と比べて、脂質(油分)が少ない代わりに糖分を多く含んでいます。そのため、濃厚な大豆の甘味と旨味を味わいつつ、低脂肪でヘルシーに食事できるのがメリットです。
そして極めつきは…青きな粉が発するきれいな黄緑のウグイス色が、めくるめくほどの明るさをもって食卓を照らします。
分類や原材料
| 分類(製法) | 生菓子 |
|---|---|
| 分類(水分量) | 餅物 |
| 主な原材料 | 求肥(白玉粉・水飴)、砂糖、小豆あん、うぐいす粉、きな粉 |
利用シーン
うぐいす餅は、早春に食べられる和菓子の代表格。春の贈り物やお祝い事、法要、お返し、手土産などに活躍します。店で買って自宅で食べるのも良いですが、できれば和菓子屋の店先で、出来立てほやほやを食べるのをおすすめします。
- 茶請け、デザート
- お祝い行事、贈り物、法要
- 手土産、お返し、お見舞い
- 運動のエネルギー補給
有名なうぐいす餅
参考資料
うぐいす餅のレビュー
歴史のある商品や、有名または知る人ぞ知る商品を厳選してレビューしています。
→ トップページへ