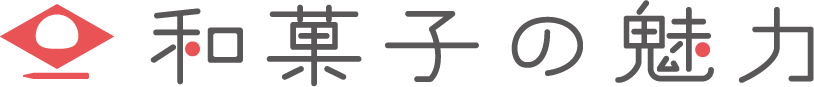由来・歴史
切山椒(きりざんしょう)の生い立ちや由来は定かではありませんが、発想の源にあるのは山椒です。
山椒の香りは古くから厄除けとしての効果が信じられてきたほか、多くの実をならせることから、子孫繁栄を願う縁起のよい素材としても重宝されてきました。
切山椒はそんな霊験あらたかな山椒をエッセンスとして取り込み、商品の売りとして活用し発展したのではないかと思われます。
そうでなければ、お餅の柔らかさや甘さを楽しむ餅菓子で、わざわざ刺激のある香辛料を使う意義を見いだすことができません。
一方、和菓子としての切山椒が歴史の表舞台に登場するのは江戸時代です。
近江小室藩初代藩主で武士にして茶人でもあった小堀政一が、切山椒を好んで食した話が伝えられており、江戸期には和菓子の一つとして認知されていたことがうかがえます。
切山椒は日本三大菓子に選ばれるなど脚光を浴びることはなかったものの、着実に広がって知名度を高めてきました。
明治以降は、夏目漱石が日記の中で「散歩中に見かけた染物屋の布が切山椒のようだった」と表現するなど、のどかな話も伝わっています。これは、切山椒が大衆に根をおろしていた証拠です。
現代においても、未だメジャーなお菓子とはいえませんが、各地に銘菓を産出するなど一定の存在感を発揮しています。
美味しく食べて災厄も打ち払う、切山椒ならではの使命にも変わりはありません。
特徴
切山椒は、スパイスの山椒を用いてつくる山形県鶴岡名物の餅菓子です。鶴岡市では12月や正月に食べる縁起菓子として知られています。
上新粉に山椒の汁または粉と砂糖を混ぜて作った生地を蒸して搗き、できあがった餅(しんこ餅)を細く短冊型に切り分けて完成します。
切山椒の形状は、厚みのある直方体で短冊形です。色は白・ピンクが定番で、他に黒糖を用いた茶色や抹茶、黄色などカラフルな配色を施したものもあります。
一方、切山椒の風味をリードするのは山椒です。餅菓子共通のもちもち食感もさることながら、一口食べるとピリッとした山椒の味と香りが広がり、一種独特のフィーリングに包まれます。
山椒は古来より厄除けの象徴として用いられてきました。その縁起をかついだ切山椒では、山椒を風味の主役とするところに最大の特徴があります。甘みや柔らかさが主となる餅菓子にあっては、実に挑戦的な大人の味わいです。
山椒の香りは独特で好みが分かれやすいため、その意味で、切山椒は八方美人な和菓子とはいえません。逆にいうと、差別化しやすく、しっかりとした個性が引き立つ和菓子でもあります。
切山椒の産地は山形県鶴岡市や山梨県甲府市が有名ですが、高知県佐川町や岩手県など各地で作られており、東京浅草の酉の市の名物としても知られています。
少なくともピリッとした風味が甘さを圧倒する餅菓子としては、当代並ぶものなしといえるでしょう。
分類や原材料
| 分類(水分量) | 半生菓子 |
|---|---|
| 分類(製法) | 蒸し物 |
| 主な原材料 | 山椒、砂糖、上新粉、黒糖、餅粉、団子粉 |
利用シーン
切山椒は行事食として多目的なシーンに対応します。お正月・節分・桃の節句・秋のお彼岸など年中行事をはじめ、お供え、祝いごと、おやつ、間食など日常使いまで幅広く利用できます。産地ではスーパーや菓子店で購入可能なほか、通販によるお取り寄せもできます。
- 年中行事、お供え、祝い事
- おやつ、お茶請け
- 手土産、贈り物
有名な切山椒
参考資料
- 冬の山梨、切山椒|全国菓子工業組合連合会
- きりせんしょ 岩手県|うちの郷土料理:農林水産省
- 山椒もち|おいしい風土こうち
- 切さんしょ -きりさんしょ-|つるおか菓子処 木村屋
- 夏目漱石と切山椒|とらや
切山椒のレビュー
*準備中です
→ トップページへ